2017年4月21日
In
一般知識
マイ照度を選べる光
日本のオフィスは部屋全体が均一に明るい場合が殆どです。それも、1000LXを超えるかなりの高照度で。勿論オフィスは働くところなので、細かい作業や図面作成などに対応できる照度環境は必要です。だからといって、部屋の隅から隅まで高照度である必要はないはずです。必要な照度は、作業内容によっても違うし、その人の視力によっても違うし、悲しいかな年齢によっても大きく違います。にもかかわらず、部屋全体で照度を固定するというのは、ひじょうに非合理的な手法です。高度経済成長期の、みな同じ目標に向かって出来るだけ効率よく仕事をこなすという時代には合っている照明だったのだと思います。まもなく、コンピューターができる仕事は殆どコンピューターに持っていかれる時代に変わろうとしている今、そろそろ照明の考え方も変えて行きたいものです。人間にしか生み出せない創造力の必要な仕事や、機械にはない感情や心の動きを敏感に働かせることなどにとっては、平坦で均一な明かりより、陰影や闇を取り入れた光環境のほうが適しています。そして、細かい作業や文字を見る為の光は、必要に応じて個々が選び調整できれば良いのです。
北欧では、オフィスの天井照明にさえ、ワーカーがマイ照度を選べるようにオン・オフできる、紐スイッチがついているオフィスも少なくないようです。それぞれの国による習慣や目の特性などもあるので、一挙に変えるというのは無理があります。(写真提供:スタジオLUME)

写真提供:スタジオLUME
まずは、ご自宅の光で試してみるのが良いかもしれません。日本の住居は、部屋の真ん中に電源がきていて、そこに取り付けた照明で部屋の明かりを均一にとる、という手法が殆どです。建売やマンションでは、ほぼ100パーセントといっていいくらいに一室一灯方式で、選択肢も与えられないのが現状だと思います。しかし、コンセントは結構あちこちにあると思いますので、置き型のスタンドなどから始めてみてはどうでしょう。
まずは寝室。寝る少し前から、部屋の照明はオフにして、低い位置のスタンドだけでストレッチや顔のお手入れなどをして過ごします。家では、娘が小学校の図工で製作してきた和紙製スタンドを使用しています。

娘作
次は、家族全員が帰宅した後には、玄関まわりの照明は消して、コンセントに差し込める簡単なフットライトなどに切り替えます。

それにも慣れてきたら、夜間は居間の明かりもアッパースタンドのみに切り替えて、間接照明のなかで過ごしてみて下さい。本を読みたければ、そこは上からのスタンドで補っていきます。
このゆな暮らし方をしていると、気が付いた時には今までの自宅の照明が眩しくてうっとおしくなっているはずです。そんな習慣が少しずつ周りに伝染していくと、世の中全体の光環境の質が上がり、省エネにも繋がっていくのですが。草の根運動は今日も続きます。

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
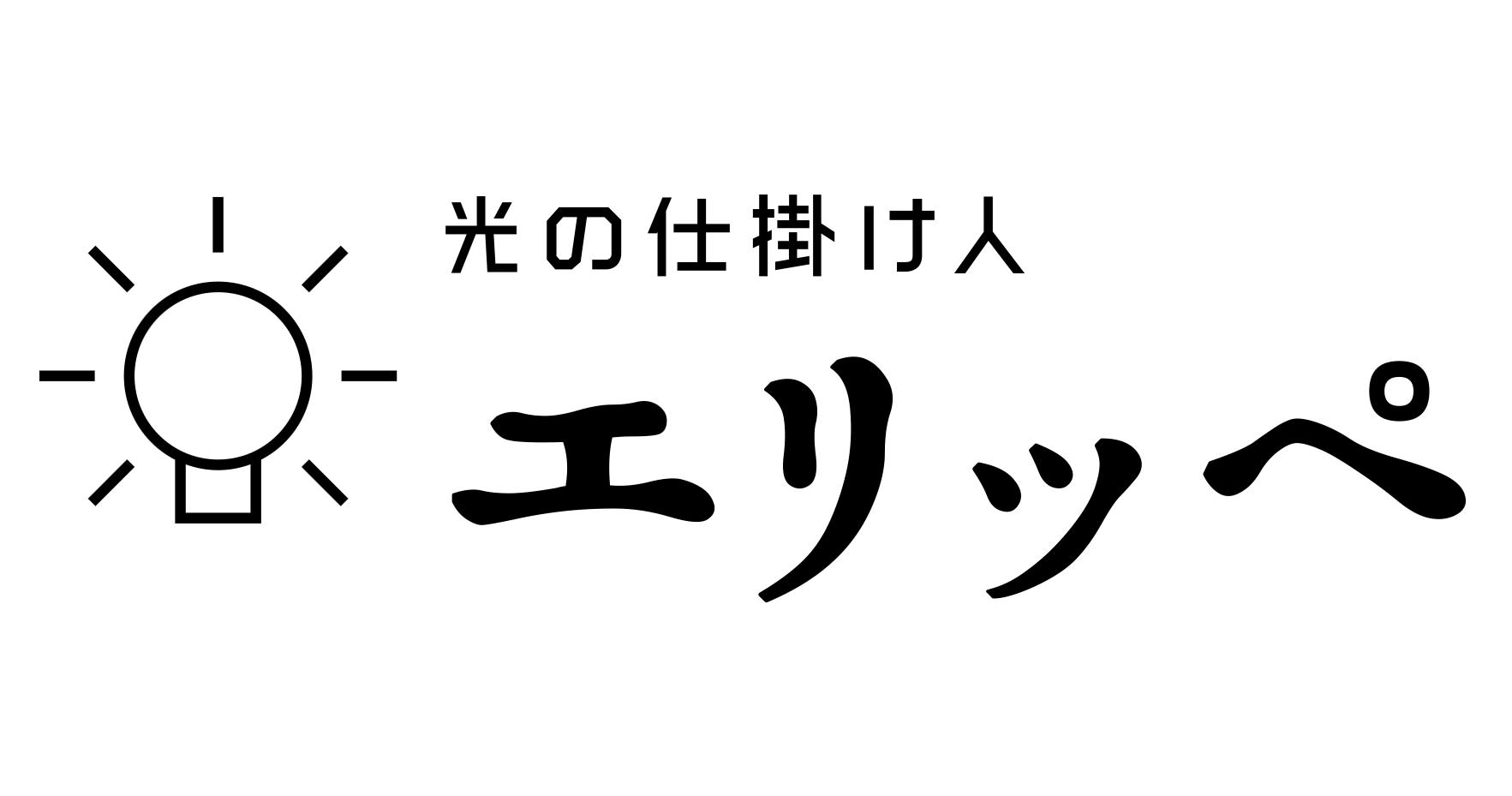

No Comments